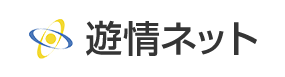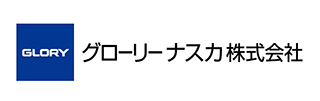- Home
- 今更聞けない?管理者のための労務管理講座 労働時間と休憩・休日④
Q 弊社では勤怠システムと絡めてタイムカードを活用しています。タイムカードの時間を労働時間とすべきなのでしょうか?そうするといろいろな問題が生じてきそうで心配です。
A 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によると労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。」とされています。
結論としてはタイムカードによる労働時間算定は絶対ではありません。おっしゃる通りタイムカードの運用は押し間違いもあれば打ち忘れもあります。また打刻システムが一台しかない場合は順番により打刻時間が変わるなどの実態もあります。タイムカードの記録=労働時間という運用は様々な問題が生じる可能性があります。
必ずしもタイムカードの記録=労働時間ではないことは、「ガイドラインについて」の通達で、「タイムカード、ICカードなどの客観的な記録をその根拠とすること、又は根拠の一部とすべきであること」としていることからも明らかです。
続きを読むには有料会員の
会員登録が必要です。
RELATED ARTICLE 関連記事
- Home
- 今更聞けない?管理者のための労務管理講座 労働時間と休憩・休日④






 超人気コンテンツ「とある科学の超電磁砲」のパチンコ第2弾がついに登場!「Pとある科学の超電磁砲2」
超人気コンテンツ「とある科学の超電磁砲」のパチンコ第2弾がついに登場!「Pとある科学の超電磁砲2」  「呪い」の向こう側へ・・・「Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer.」
「呪い」の向こう側へ・・・「Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer.」  これはボーナスへの挑戦。「Pルパン三世ONE COLLECTION」
これはボーナスへの挑戦。「Pルパン三世ONE COLLECTION」  東京都公安委員会検定通過状況(7月16日)
東京都公安委員会検定通過状況(7月16日)  MIRAI7月度定例理事会 「未来のファン創造」に向けた委員会活動を報告
MIRAI7月度定例理事会 「未来のファン創造」に向けた委員会活動を報告