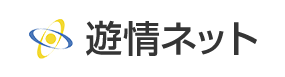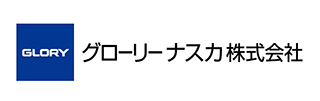- Home
- 大衆と愛好者のどちらを顧客としたいのだろうか
マーケティングには、消費者行動という分野がある。消費者行動とは、「人がものやサービスを購入して使用するまでの過程の行動」を指し、物理的な行動だけでなく心理的な動きや変化も含んでいる。
消費者行動の観点から見ると、かつてのパチンコ・パチスロは「○○のついでに遊技場に寄って遊ぶもの」であった。○○には、通勤・通学、学校の講義や会社の昼休み、出張の乗り換え、日々の買い物など、消費者それぞれによって異なるのは言うまでもない。つまり、様々な消費者が来店することができたからこそ、大衆娯楽たりえたのであろう。
続きを読むには有料会員の
会員登録が必要です。
RELATED ARTICLE 関連記事
- Home
- 大衆と愛好者のどちらを顧客としたいのだろうか






 超人気コンテンツ「とある科学の超電磁砲」のパチンコ第2弾がついに登場!「Pとある科学の超電磁砲2」
超人気コンテンツ「とある科学の超電磁砲」のパチンコ第2弾がついに登場!「Pとある科学の超電磁砲2」  これはボーナスへの挑戦。「Pルパン三世ONE COLLECTION」
これはボーナスへの挑戦。「Pルパン三世ONE COLLECTION」  「呪い」の向こう側へ・・・「Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer.」
「呪い」の向こう側へ・・・「Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer.」  東京都公安委員会検定通過状況(7月16日)
東京都公安委員会検定通過状況(7月16日)  MIRAI7月度定例理事会 「未来のファン創造」に向けた委員会活動を報告
MIRAI7月度定例理事会 「未来のファン創造」に向けた委員会活動を報告